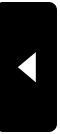夕景!
昨日は一日曇りが続きましたが 夕刻になり山の端の隙間にお日様が顔を出して呉れました。

18時35分の映像です。 お日様は次第に比叡山に近く沈む季節になりました。

18時42分です。 次第に雲が取れて来ました。

同時刻のズーム映像です。 真ん丸なお日様です。 思い出しました。
確か今夜は満月だと~~~ 残念ながら 映像は撮れませんでしたが・・・
20時過ぎには 晴れて来て頭上に輝いていたんですが・・・ 早朝にお日様と同じような位置に
沈むはずだと・・・ 処が寝過ごし既に強い朝日に敗けて・・・色褪せてか?
行方が判らなくなっていたんです。
18時35分の映像です。 お日様は次第に比叡山に近く沈む季節になりました。
18時42分です。 次第に雲が取れて来ました。
同時刻のズーム映像です。 真ん丸なお日様です。 思い出しました。
確か今夜は満月だと~~~ 残念ながら 映像は撮れませんでしたが・・・
20時過ぎには 晴れて来て頭上に輝いていたんですが・・・ 早朝にお日様と同じような位置に
沈むはずだと・・・ 処が寝過ごし既に強い朝日に敗けて・・・色褪せてか?
行方が判らなくなっていたんです。

昨日は甲賀へ
昨日は土曜日に予定していた山行が雨で中止になり、日中は雨も無さそうで
つい 出掛けて来ました~~~(笑)

こんな所です。 標高は余り高く無く大きな岩が名物の山ですね~~~
岩尾山・471Mです。
麓には明治時代に出来た大きな灌漑用の池が二つ有ります。 岩尾池と大沢池!

岩尾池の湖畔にはこの様に老い杉の大木が鎮座しています。 岩尾池の大杉として
知る人ぞ知る! 何処かの映画の撮影にも使われたとか~~~

池の水量が多い時には、湖畔に佇む・・・景色ですが、近年は水量が少なく周りの砂浜が
広く池から離れたように見えますネ~~~

此れはアカマツの新芽です。 既に今年の雄花は半分以上落ちていて、昨年の雌花からは若い実が
出来ていました。 この枝では1個だけですが、2~3個付いている枝が多いです。

枝の先端には この様に少し紅い今年の雌花が付いていました。 受精して来年には
小さい実と成って居るようです。

愈々 山に入りましたが… 苔生した岩肌に芭蕉の句が刻まれていたようですが( ^ω^)・・・
全然見えませんでした。

登り始めると 此の様な大岩がゴロゴロ~~~ 山の名前の訳が好く理解できました。

この岩は 天狗岩との名前! 根元には仲良く二体の石仏が~
四国八十八ヶ所と書かれていましたが、後で紹介する大岩の周りを巡る山道に配置されている
石仏さんです。

制作年代などは? 可愛い感じの仏様ですね~~~


此の後 県境の尾根を進み 岩尾山・471mと 岩尾山西峰・460mに立ちました。

山頂で見掛けた、ジンチョウゲ科のガンピの若葉です。 既に蕾を附けていました。
高級和紙の雁皮紙の材料です。 此処ではバラ科のカマツカの若葉も見掛けました。

巨大な一枚岩は信仰の対象か? 息障寺の奥の院が祀られていました。 この岩の上は鈴鹿山系を
望める展望台と成っていました。

馬の背の様に見えるんでしょう! お馬岩。

此方は 木魚岩。

此の様な急な石階段が五回も続いて居ました。 何とも大きな岩でしたね~~~屏風岩。

此処の岩尾山の息障寺の境内に降りて来ました。 池の周りの水辺に自生していました。
タツナミソウが満開でしたね~


帰りに 大沢池と岩尾池の間の堰堤に群生して咲いていた ハルリンドウは色も濃くて
とても綺麗でした。
今回は此れまでです。
つい 出掛けて来ました~~~(笑)
こんな所です。 標高は余り高く無く大きな岩が名物の山ですね~~~
岩尾山・471Mです。
麓には明治時代に出来た大きな灌漑用の池が二つ有ります。 岩尾池と大沢池!
岩尾池の湖畔にはこの様に老い杉の大木が鎮座しています。 岩尾池の大杉として
知る人ぞ知る! 何処かの映画の撮影にも使われたとか~~~

池の水量が多い時には、湖畔に佇む・・・景色ですが、近年は水量が少なく周りの砂浜が
広く池から離れたように見えますネ~~~
此れはアカマツの新芽です。 既に今年の雄花は半分以上落ちていて、昨年の雌花からは若い実が
出来ていました。 この枝では1個だけですが、2~3個付いている枝が多いです。
枝の先端には この様に少し紅い今年の雌花が付いていました。 受精して来年には
小さい実と成って居るようです。
愈々 山に入りましたが… 苔生した岩肌に芭蕉の句が刻まれていたようですが( ^ω^)・・・
全然見えませんでした。
登り始めると 此の様な大岩がゴロゴロ~~~ 山の名前の訳が好く理解できました。
この岩は 天狗岩との名前! 根元には仲良く二体の石仏が~
四国八十八ヶ所と書かれていましたが、後で紹介する大岩の周りを巡る山道に配置されている
石仏さんです。
制作年代などは? 可愛い感じの仏様ですね~~~
此の後 県境の尾根を進み 岩尾山・471mと 岩尾山西峰・460mに立ちました。
山頂で見掛けた、ジンチョウゲ科のガンピの若葉です。 既に蕾を附けていました。
高級和紙の雁皮紙の材料です。 此処ではバラ科のカマツカの若葉も見掛けました。
巨大な一枚岩は信仰の対象か? 息障寺の奥の院が祀られていました。 この岩の上は鈴鹿山系を
望める展望台と成っていました。
馬の背の様に見えるんでしょう! お馬岩。
此方は 木魚岩。
此の様な急な石階段が五回も続いて居ました。 何とも大きな岩でしたね~~~屏風岩。
此処の岩尾山の息障寺の境内に降りて来ました。 池の周りの水辺に自生していました。
タツナミソウが満開でしたね~
帰りに 大沢池と岩尾池の間の堰堤に群生して咲いていた ハルリンドウは色も濃くて
とても綺麗でした。
今回は此れまでです。

初夏の信楽路
さて 信楽路を続けて参ります。

此れは栽培種なので 本来の野草では有りませんが、「余りにも綺麗でつい見とれてしまいました。
大輪の赤いボタンと 白いコデマリが咲き誇っていました。 道沿いの民家さんのでした。

此方も綺麗ですが 此れは帰化植物の ケシ科 ナガミノヒナゲシです。
既に花弁が落ちてその名前の由来通り 長い実が出来ていました。



此れは同じく道沿いのお庭や壁際に飾られていた干支の動物達です。
流石は信楽の街です。 コンナンが普通に民家の飾りに並んでいるんです。

咲き始めたばかりの バラ科キジムシロ属の ヘビイチゴです。

立冬の森にも有りますが 此処のは小さい上に背も低いです。 スミレ科の ツボスミレです。
又の名を如意スミレとも言います。
白い花の唇弁には青い線模様が入り 綺麗です。

スイカズラ科の ツクバネウツギも満開でした~~~


花はこの様に咲いていましたが 葉は未だ幼く小さかったし 溝の向かいで遠くて手に入りませんでした。
好~く花の下の葉を観ると7枚の奇数羽状複葉の様で モクセイ科トネリコ属の アオダモとしました。

ガマズミ科の コバノガマズミは此処でも多く見掛けました。
その後 玉桂寺を経て 信楽駅に迄着きました。

駅前の大狸君の 此の日の衣装は 股旅姿でした。

その後 街中をチャリで散策しました。 この様は信楽焼屋さんが沢山有りましたが
陶器市が終わったばかりか? 人気は余り感じませんでした。
此れは栽培種なので 本来の野草では有りませんが、「余りにも綺麗でつい見とれてしまいました。
大輪の赤いボタンと 白いコデマリが咲き誇っていました。 道沿いの民家さんのでした。
此方も綺麗ですが 此れは帰化植物の ケシ科 ナガミノヒナゲシです。
既に花弁が落ちてその名前の由来通り 長い実が出来ていました。
此れは同じく道沿いのお庭や壁際に飾られていた干支の動物達です。
流石は信楽の街です。 コンナンが普通に民家の飾りに並んでいるんです。
咲き始めたばかりの バラ科キジムシロ属の ヘビイチゴです。
立冬の森にも有りますが 此処のは小さい上に背も低いです。 スミレ科の ツボスミレです。
又の名を如意スミレとも言います。
白い花の唇弁には青い線模様が入り 綺麗です。
スイカズラ科の ツクバネウツギも満開でした~~~
花はこの様に咲いていましたが 葉は未だ幼く小さかったし 溝の向かいで遠くて手に入りませんでした。
好~く花の下の葉を観ると7枚の奇数羽状複葉の様で モクセイ科トネリコ属の アオダモとしました。
ガマズミ科の コバノガマズミは此処でも多く見掛けました。
その後 玉桂寺を経て 信楽駅に迄着きました。
駅前の大狸君の 此の日の衣装は 股旅姿でした。
その後 街中をチャリで散策しました。 この様は信楽焼屋さんが沢山有りましたが
陶器市が終わったばかりか? 人気は余り感じませんでした。
初夏の信楽路
今日からは低気圧の通過で何日かは春の嵐の気配です。
昨日は其れを見越して 上天気の中 信楽路を自然観察をしながらユックリと
チャリって来ました。 春の花は終盤で そろそろ夏向きの花に替わりつつある中
少ない花数でした。

キク科 オニタビラコです。

キンポウゲ科の キツネノボタン。

此れは タデ科の スイバの花です。

マメ科の スズメノエンドウ。

此れも花なんです。 イグサ科の スズメノヤリ。

フウロソウ科の アメリカフウロ。

オオバコ科の オオイヌノフグリ。

カタバミ科の カタバミ。 朝早いのか?未だ花が開花し切っていませんでした。

ナデシコ科の オランダミミナグサ。 此れも未だ蕾んでいました。

アブラナ科の ナズナ。ぺんぺん草とも言われていますね~
チャリを車に積んで行き、信楽高原鉄道の勅旨駅に停めて チャリを組み立てての出発ですが
駅の周りの地面には沢山の野草が咲き乱れていました。 勿論 タンポポなど此処には紹介しなかった花も
幾つか有りますが・・・ 此の日は往復8kmほどを ユックリ走り時には押して歩きながらの
観察でした。 残りは明日からです。
昨日は其れを見越して 上天気の中 信楽路を自然観察をしながらユックリと
チャリって来ました。 春の花は終盤で そろそろ夏向きの花に替わりつつある中
少ない花数でした。
キク科 オニタビラコです。
キンポウゲ科の キツネノボタン。
此れは タデ科の スイバの花です。
マメ科の スズメノエンドウ。
此れも花なんです。 イグサ科の スズメノヤリ。
フウロソウ科の アメリカフウロ。
オオバコ科の オオイヌノフグリ。
カタバミ科の カタバミ。 朝早いのか?未だ花が開花し切っていませんでした。
ナデシコ科の オランダミミナグサ。 此れも未だ蕾んでいました。
アブラナ科の ナズナ。ぺんぺん草とも言われていますね~
チャリを車に積んで行き、信楽高原鉄道の勅旨駅に停めて チャリを組み立てての出発ですが
駅の周りの地面には沢山の野草が咲き乱れていました。 勿論 タンポポなど此処には紹介しなかった花も
幾つか有りますが・・・ 此の日は往復8kmほどを ユックリ走り時には押して歩きながらの
観察でした。 残りは明日からです。

鈴鹿の山芍薬 ③
さぁ~ 山芍薬の自生している鈴鹿の山の続きです。
既に葉を出し次第に緑を濃くしている樹木も有れば、冬芽を開き未だ先っぽを出し始めた
ばかりの新緑とも云えぬ幼い葉の樹木等~~~ 様々な春を感じる林内です。

標高650m辺りでした。 未だ咲き残っていた キンポウゲ科のムラサキケマンです。

山頂と山頂を結ぶなだらかな尾根筋の杉が伐採されていて大きく視界が開けていました。
湖東の町々や遠く 三上山、繖山、八幡山等が見通せました。 少し右側には対岸の
比良山系も遠望出来ました。 春の近江の景色ですね~~~


なだらかな尾根筋や 下山中の斜面にも次々と ヤマシャクヤクの群落が現れて天国の様でした。

真近に見上げる 霊仙山・1090m辺りが堂々としていました。


此の辺りでは サトイモ科の ウラシマソウの群落も見えました~~~

ナデシコ科の ミヤマハコベも沢山咲いていました。

トウダイグサ科の ナツトウダイも所々で見掛ける事が出来ました。

此処ではほんの一輪のみでした。(笑) キンポウゲ科の イチリンソウも観ることが出来ました。
今回の花旅は此処までです~~~ 花の多い此の季節です。 週末にも計画していますが
次々と春雨が襲来しています。 さ~行けるのかなぁ???
既に葉を出し次第に緑を濃くしている樹木も有れば、冬芽を開き未だ先っぽを出し始めた
ばかりの新緑とも云えぬ幼い葉の樹木等~~~ 様々な春を感じる林内です。
標高650m辺りでした。 未だ咲き残っていた キンポウゲ科のムラサキケマンです。
山頂と山頂を結ぶなだらかな尾根筋の杉が伐採されていて大きく視界が開けていました。
湖東の町々や遠く 三上山、繖山、八幡山等が見通せました。 少し右側には対岸の
比良山系も遠望出来ました。 春の近江の景色ですね~~~

なだらかな尾根筋や 下山中の斜面にも次々と ヤマシャクヤクの群落が現れて天国の様でした。
真近に見上げる 霊仙山・1090m辺りが堂々としていました。
此の辺りでは サトイモ科の ウラシマソウの群落も見えました~~~
ナデシコ科の ミヤマハコベも沢山咲いていました。
トウダイグサ科の ナツトウダイも所々で見掛ける事が出来ました。
此処ではほんの一輪のみでした。(笑) キンポウゲ科の イチリンソウも観ることが出来ました。
今回の花旅は此処までです~~~ 花の多い此の季節です。 週末にも計画していますが
次々と春雨が襲来しています。 さ~行けるのかなぁ???

鈴鹿の山芍薬 ②
山芍薬を見た時に 同時に見掛けられた花さん達です~~~ ご覧下さい!!!

サトイモ科 テンナンショウ属の カラスビシャクでした。
マムシグサと好く似ていますが、苞が細いですね~~~

ムラサキ科の ヤマルリソウです。 とっても綺麗な紫色の花ですね~~~ 勿忘草はこの種の栽培種です。

此れが葉で 上から見た所・・・ 対生です。

此方は葉の下側からの映像です。 花が沢山咲いていますね~~~
ムクロジ科 カエデ属の チドリノキです。
カエデの仲間なのに珍しく葉が割けていません。
面白い例外です。

直ぐお隣に好く似たこの葉が有りました。 葉は互生で明らかにチドリノキとは違います。
葉の付け根は心形でしょう! カバノキ科の サワシバの様ですね~~~
何方も薄緑色の柔らかい綺麗な若葉でした。

此方は未だ芽吹いて間もない ムクロジ科の トチノキの若葉です~~~

此の花は ムクロジ科の ウリハダカエデです。

此方にも可愛い白い花~~~ ユリ科の チゴユリですね~~~
今日も此処までです~~~ もう少し花を観ていますので 明日にでも~
サトイモ科 テンナンショウ属の カラスビシャクでした。
マムシグサと好く似ていますが、苞が細いですね~~~
ムラサキ科の ヤマルリソウです。 とっても綺麗な紫色の花ですね~~~ 勿忘草はこの種の栽培種です。
此れが葉で 上から見た所・・・ 対生です。
此方は葉の下側からの映像です。 花が沢山咲いていますね~~~
ムクロジ科 カエデ属の チドリノキです。
カエデの仲間なのに珍しく葉が割けていません。
面白い例外です。
直ぐお隣に好く似たこの葉が有りました。 葉は互生で明らかにチドリノキとは違います。
葉の付け根は心形でしょう! カバノキ科の サワシバの様ですね~~~
何方も薄緑色の柔らかい綺麗な若葉でした。

此方は未だ芽吹いて間もない ムクロジ科の トチノキの若葉です~~~
此の花は ムクロジ科の ウリハダカエデです。
此方にも可愛い白い花~~~ ユリ科の チゴユリですね~~~
今日も此処までです~~~ もう少し花を観ていますので 明日にでも~

鈴鹿の山芍薬
今日は連休の最終日! 然も予想されてた通りの終日の雨模様( ^ω^)・・・
お休み疲れの方々には 身体を休める良い休日?かな~~~?
昨日は鈴鹿山系に出掛けて来ました。 この時期のお花を観る為です。 ご覧下さい!


新鮮な花を観ることが出来ました。 登山口から何分も歩いて無いのに~です。



花弁を落としたものは雌蕊の子房が育ち始めていました。 紅い実を育てます。
ボタン科のヤマシャクヤク(山芍薬)です。 何とも清楚な花弁で有るのに花の中の雄蕊、雌蕊は妖艶さを感じます。
此の日は全山登山口から山頂、尾根筋迄~~~ 群生している白い花を 何処にでも見られました。
因みに 昨年の6月初めには 紅花ヤマシャクヤクも見に行っていました。
アップした筈のブログを探して見ました。 https://akojunmai.shiga-saku.net/d2024-06-07.html⇔ここをクリックして下さい!
綺麗な紅花ヤマシャクヤクを御覧になれますね~~~
お休み疲れの方々には 身体を休める良い休日?かな~~~?
昨日は鈴鹿山系に出掛けて来ました。 この時期のお花を観る為です。 ご覧下さい!
新鮮な花を観ることが出来ました。 登山口から何分も歩いて無いのに~です。
花弁を落としたものは雌蕊の子房が育ち始めていました。 紅い実を育てます。
ボタン科のヤマシャクヤク(山芍薬)です。 何とも清楚な花弁で有るのに花の中の雄蕊、雌蕊は妖艶さを感じます。
此の日は全山登山口から山頂、尾根筋迄~~~ 群生している白い花を 何処にでも見られました。
因みに 昨年の6月初めには 紅花ヤマシャクヤクも見に行っていました。
アップした筈のブログを探して見ました。 https://akojunmai.shiga-saku.net/d2024-06-07.html⇔ここをクリックして下さい!
綺麗な紅花ヤマシャクヤクを御覧になれますね~~~

今日の戴き物
今日のお昼過ぎ 此の様な戴き物が宅急便で着きました!



もう分かりましたね〜 そうですお魚! 養殖銀鮭でした~

約2kg! 丸々と肥って居ます!
頭が小さく見えるのが其の証!
さて今夜のおかずのメニューは?



もう分かりましたね〜 そうですお魚! 養殖銀鮭でした~

約2kg! 丸々と肥って居ます!
頭が小さく見えるのが其の証!
さて今夜のおかずのメニューは?
オオイワカガミ
昨日 アップさせて頂いているオオイワカガミですが、色の違うのが有るので観て下さい!

一つは此れ! 花びらの色は、薄いピンク。

もう一つは此れ! 鮮やかな紅色。
何方も標高500~600m辺りで満開でした! 標高が上がれば未だ此れからも楽しめそうですね~

此方は イワウチワで、イワカガミに較べると咲いてる高度は少し高く700~800m辺りが中心でした。

此方は未だ蕾でしたが、ツツジ科のサラサドウダンの様でした。

此方はユリ科のユキザサの幼い葉と蕾ですね~ これから愉しませて呉れる事でしょう!

此方は既に散りかかって居ました!
花の付け根に1枚の葉を付けてるコブシですね~
葉の無いタムシバも此処では見掛けた事を書き添えます。
季節の移ろいと共に色んな花が咲き愉しませて呉れる此のエリアです!
次回も乞うご期待!

一つは此れ! 花びらの色は、薄いピンク。

もう一つは此れ! 鮮やかな紅色。
何方も標高500~600m辺りで満開でした! 標高が上がれば未だ此れからも楽しめそうですね~

此方は イワウチワで、イワカガミに較べると咲いてる高度は少し高く700~800m辺りが中心でした。

此方は未だ蕾でしたが、ツツジ科のサラサドウダンの様でした。

此方はユリ科のユキザサの幼い葉と蕾ですね~ これから愉しませて呉れる事でしょう!

此方は既に散りかかって居ました!
花の付け根に1枚の葉を付けてるコブシですね~
葉の無いタムシバも此処では見掛けた事を書き添えます。
季節の移ろいと共に色んな花が咲き愉しませて呉れる此のエリアです!
次回も乞うご期待!

今日は大御影山へ
先週の土曜日は鈴鹿の釈迦ヶ岳に行きましたが、今日は高島の奥の大御影山でのお花見でした~

イカリソウ!

オオイワカガミ!

イワナシ!

イワウチワとカタクリ!

オオバノキスミレ!

ショウジョウバカマとカタクリ!

何とキンキマメザクラ!も

ニホンシャクナゲ!

バイカオウレン!

エンレイソウ!
等々〜 正に当たり!
一年で一番の花の季節に出逢う事が出来、至福の山歩きと成りました!


イカリソウ!

オオイワカガミ!

イワナシ!

イワウチワとカタクリ!

オオバノキスミレ!

ショウジョウバカマとカタクリ!

何とキンキマメザクラ!も

ニホンシャクナゲ!

バイカオウレン!

エンレイソウ!
等々〜 正に当たり!
一年で一番の花の季節に出逢う事が出来、至福の山歩きと成りました!